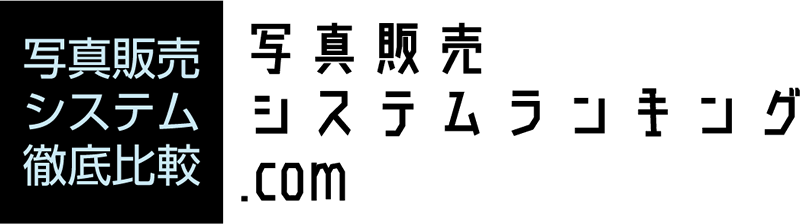画期的なスマートフォンのアプリが登場しました。
白黒写真をダウンロードし、色を加えるボタンをタップします。
するとAI(人工知能)が数十秒以内に画像へ色彩を施してくれるのです。
電柱や路面電車が写る戦前の那覇の街並みが、カラーで鮮やかに蘇るとのことで、驚きを隠せません。
(※2025年5月4日 朝日新聞の記事を参考に要約しています。)
昔の記憶に色を灯す、AI技術の進化
大阪市に住む会社員のホリーニョさん(45歳、本名非公開)は、太平洋戦争の前後に撮影された沖縄の写真をカラー化する活動に注力しています。
赤瓦の家屋や、頭の上に荷物を乗せて歩く人々の姿など、これまでに300枚を超える写真に色を加えました。
彼の写真集は那覇市内の書店で売上1位を記録しました。
白黒写真に色を加える取り組みは、歴史への関心を高める手段として広まりつつあります。
朝日新聞をはじめとする報道機関も、専門家の助言を得ながら、当時を知る人々の証言をもとにカラー化に取り組んでいます。
また、AIの技術が進化したことで、静止画から動画を作ることも可能になりました。
上海出身のショーン・シャオさん(35歳)は、AIを活用した事業を2024年8月に日本で開始しました。
彼の地元・中国ではビジネスの模倣が早いため、日本での展開を決意したとのことです。
数分で白黒写真をカラー動画に変換できる技術を用い、祖母の笑顔を引き出すために最初の作品を制作しました。
若き日の祖父との1枚の写真が、動きのある動画に生まれ変わった瞬間、祖母は久しぶりに笑顔を見せたそうです。
歴史をテーマにした動画の人気も高まっています。
特攻隊員が笑顔で手を振る動画は48万回再生され、「笑う」「手を振る」といった指示をAIに与えることで実現できます。
原爆投下後の広島でがれきの中に立つ青年や、負傷して顔をしかめる少女を再現した動画も18万回再生されました。
今年4月、シャオさんの作品展を訪れた58歳の女性は「動画は心に響きます。写真よりも感情が伝わります」と語っていました。
情報の信頼性が問われる時代、AI画像と歴史の境界線
AIの技術が進歩したことで、写真や映像の加工精度が飛躍的に向上しています。
その結果、真実と創作の見分けがつきにくくなってきたことに、不安の声が広がっています。
とくに、歴史的資料としての写真や動画が、AIによる加工で改変され、その説明が不十分なままインターネット上に拡散される事態が懸念されています。
オランダの歴史研究者であるヨー・ヘドウィグ・テウィセさん(52歳)は、自らを「Fake History Hunter(偽の歴史を追う者)」と名乗り、ネット上に存在する誤った歴史情報の指摘活動を8年間続けています。
彼が特に注目しているのは、2023年以降に急増したAIによる偽造画像や動画の存在です。
「当初は細流のようでしたが、今では氾濫状態です。見かけない日はありません」と話しています。
象徴的な例として、1912年に発生したタイタニック号沈没事故から生還したとされる兄弟の写真があります。
Facebook上の歴史ファンのグループで「兄弟の生還写真」として広まった画像には、2人の少年が似た体格で写っていますが、テウィセさんは不自然さに気づきました。
手が3つあるように見えたり、ボタンがないシャツが閉じていたりするなどの違和感があったため調査を行ったところ、それはAI生成による偽物だと判明しました。
実際の写真では、当時2歳の弟は4歳の兄よりも明らかに小柄で、髪質も異なっていたとのことです。
しかし、誤情報の拡散は止まらず、4月下旬に投稿されたこの画像は、10日間で25万件の「いいね」と8,400件以上のコメントを集めました。
コメントの中には、偽造を指摘するものもありますが、「この兄弟が助かって本当によかった」と信じている様子の書き込みも数多く見受けられます。
歴史と信頼の境界が揺らぐ時代に
テウィセさんは、「現在作られた偽の歴史画像が、誤って書籍や資料に引用される可能性があります。
その結果、将来の歴史研究者が正確な検証を行うことが非常に困難になるでしょう」と懸念を示しています。
もし、このような偽情報に悪意が加われば、さらに深刻な事態を招く可能性があります。
フェイク情報の研究を行っている国立情報学研究所の越前功教授は、「信頼性の高い情報源さえも、気づかぬうちに書き換えられていく」と警告を発しています。
現実に、インターネット上では意図的に仕組まれた偽の情報が拡散しています。
越前教授によれば、
「専門知識を持つ人間でも見分けが難しいような高精度な偽画像を、誰でも作れる時代になりました。その影響で、人々の認識が知らず知らずのうちに操作されていくことになります。長期的に見れば、生成AIは言論の自由にとって極めて大きな脅威となる可能性があります」
と述べています。